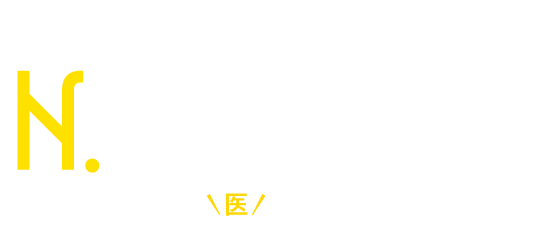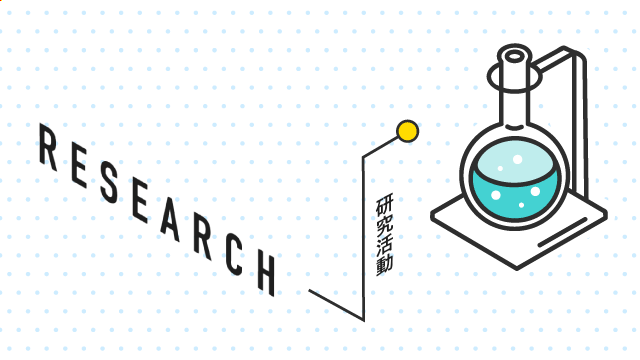東京医科大学(学長:宮澤啓介/東京都新宿区)薬理学分野 草苅伸也講師と金蔵孝介主任教授、同大学医学総合研究所 須藤カツ子非常勤講師らの研究グループは、神経保護因子として機能するプログラニュリン(PGRN)が過剰に働いてしまうことで、本来の機能とは逆に神経毒性を引き起こすことを見出しました。さらに、このPGRNによる神経毒性はPGRNの発現量の増加に伴って増強することを明らかにしました。この研究成果は、2025年4月1日、国際神経生物学誌「Neurobiology of Disease」に掲載されました。
【概要】
東京医科大学(学長:宮澤啓介/東京都新宿区)薬理学分野 草苅伸也講師と金蔵孝介主任教授、同大学医学総合研究所 須藤カツ子非常勤講師らの研究グループは、神経保護因子として機能するプログラニュリン(PGRN)が過剰に働いてしまうことで、本来の機能とは逆に神経毒性を引き起こすことを見出しました。さらに、このPGRNによる神経毒性はPGRNの発現量の増加に伴って増強することを明らかにしました。
現在、PGRNをコードするグラニュリン(GRN)遺伝子の遺伝子変異による前頭側頭型認知症(Frontotemporal dementia:FTD)に対する治療としてPGRNの補充療法の開発が進められております。本研究成果は、安全なPGRN補充療法の確立に貢献することが期待されます。
この研究成果は、2025年4月1日、国際神経生物学誌「Neurobiology of Disease」に掲載されました。
【本研究のポイント】
●ヒトPGRNを過剰発現するトランスジェニック(Tg)マウス*¹はFTDに類似した病態を示した。
●FTD発症に関わるPGRN変異体(MT) TgマウスもFTD様の行動異常と神経細胞死を示した。
●培養細胞におけるPGRNの過剰発現は細胞死を引き起こした。
【研究の背景】
前頭側頭型認知症(FTD)は、前頭および側頭葉の萎縮によって起こる認知症で、65歳未満で発症する若年性認知症の主な原因のひとつとなっています。認知機能障害のほかに特徴的な症状として人格変化や行動障害、失語症、運動障害などがあり、これらの症状は緩徐に進行していきます。FTD患者の一部は遺伝性であり、現在までに神経細胞内への異常タンパク質の凝集と蓄積がFTD発症に関わることが明らかになりつつありますが、治療薬の確立には至っておりません。
神経保護機能を有するPGRNをコードするGRN遺伝子は、2006年にFTD原因遺伝子として同定され、これまでに259のFTD患者家系からFTD発症に関わるGRN変異が少なくとも79個見つかっています。GRN遺伝子変異のほとんどは、ナンセンス変異やフレームシフト変異、スプライス部位変異であり、これらの変異によって本来存在しないところに停止コドンが新たに生じ、異常なmRNAが作られてしまいます。このような異常mRNAは、mRNAの品質管理を担うナンセンス変異依存分解機構(NMD)²によって分解されてしまうため、GRN変異を有するFTD患者ではPGRNの発現量が低下しています。このため、PGRNのハプロ不全³がFTDの病因において中心的な役割を果たすと考えられており、低下したPGRNを補う補充療法が注目されています。これまでに、GRN遺伝子変異によるFTDの症状を模倣するGRN遺伝子改変マウスにおいて、ウイルスベクター*⁴を用いたPGRNの補充によってFTD様の行動異常が改善することが報告され、PGRN補充療法の臨床応用に向けた解析が進められています。しかしながら、体内でのPGRNの高発現が予期せぬ問題などを引き起こさないかどうかについては十分検討されておらず、PGRN補充療法を実現する上で重要な課題となっています。
【本研究で得られた結果・知見】
GRN遺伝子変異によって発症するFTDに対するPGRNの補充療法として、現在、ウイルスベクターを用いた過剰発現やリコンビナントタンパク質の投与のほか、長期的な補充を実現するために遺伝子操作によってGRN遺伝子をゲノム内に導入し、過剰発現させる方法が用いられています。今回、我々はPGRNの長期的な補充が生体に与える影響について観察するため、正常な遺伝子型である野生型(WT)ヒトPGRNを過剰発現するTgマウス(WT Tg)を作製しました。作製したWT Tgマウスでは、寿命が短くなり、認知機能障害や小脳機能異常による運動障害が認められました。さらに、組織学的解析から、WT Tgマウスでは小脳のプルキンエ細胞の細胞死による脱落のほか、FTD患者脳でも観察されるグリア細胞*⁵の異常増殖が認められ、ヒトPGRNの過剰発現がFTDに非常によく似た病態を引き起こすことが明らかとなりました。
また、FTDの発症に関わるPGRNの変異体を過剰に発現するTgマウス(MT Tg)を作製し、解析した結果、MT TgマウスもFTD様の症状を示し、さらにWT Tgマウスでは認められなかった大脳皮質の萎縮や海馬神経細胞死、行動異常など、より重篤な病態となることが明らかとなりました。
さらに、培養細胞を用いて、PGRNの発現量の増加がFTDの病因となる細胞死を引き起こすか検討したところ、PGRN発現量増加に伴って細胞死が誘導されることが明らかとなりました。
以上の結果から、ウイルスベクターや遺伝子操作などによるPGRNの継続的な発現増加には神経毒性があり、安全にPGRN補充療法を行うには神経細胞のタイプや脳部位に従って適切なPGRNレベルを維持する必要があることが明らかとなりました。
【今後の研究展開および波及効果】
GRN遺伝子変異FTDの治療としてPGRN補充療法が開発され、現在、臨床試験が進められております。これらの試験では一定の効果を示すことが報告されている一方で、PGRN補充による神経毒性と推測されるデータが示されており、PGRN補充療法を実現する上で重要な課題と考えられます。
本研究成果は、安全にPGRN補充療法を行うための基盤として応用されることが期待されます。また、PGRNは神経保護のほか、抗炎症作用や血管保護など多様な保護機能を有することから、FTD治療のみならず、免疫疾患をはじめとする様々な疾患への応用が期待されています。これらへの安全な利用に対しても、本研究成果が寄与することが期待されます。
【論文情報】
タイトル:Excessive expression of progranulin leads to neurotoxicity rather than neuroprotection
著 者:Shinya Kusakari, Hiroaki Suzuki, Mikiro Nawa, Katsuko Sudo, Rio Yamazaki, Tamami Miyagi, Tomoko Ohara, Masaaki Matsuoka, Kohsuke Kanekura*(:責任著者)
掲載誌名:Neurobiology of Disease
DOI : https://doi.org/10.1016/j.nbd.2025.106895
【主な競争的研究資金】
本研究は文部科学省科学研究費補助金 基盤(C)【草苅(JP16K08557, JP19K07329, 23K06369)、鈴木(24K09851)、名和(21K07284)】 、基盤(B)【松岡(15H04689)、 金蔵(24K02187)】、先進医薬研究振興財団【草苅】、武田科学振興財団【草苅、鈴木】、大樹生命厚生財団【草苅、鈴木】、三井住友海上福祉財団【草苅】、薬学研究奨励財団【草苅】、東京医科大学研究助成の支援を受けて行われました。
【用語の解説】
*1:トランスジェニックマウス(Tgマウス)
遺伝子改変マウスの一種で、人工的な操作により外来性に目的遺伝子を導入することで目的遺伝子の発現量を増強したマウス。
*2:ナンセンス変異依存分解機構(NMD)
ヒトを含む真核生物がもつmRNA品質管理機構のひとつで、ゲノムの突然変異や転写・スプライシングの間違いなどによって未成熟な終止コドンが生じた場合、異常なmRNAを選択的に分解することで、不完全なタンパク質が作られてしまうことを阻止する。
*3:ハプロ不全
一対の遺伝子のうちの1つに変異があり、残りの正常遺伝子から作られる正常タンパク質だけでは量が不足してしまい、正常な機能を維持することができない状態。
*4:ウイルスベクター
ウイルスは感染した宿主に自らのゲノムを送り込み、宿主が持つ転写翻訳機構を利用しウイルス自身のゲノムを複製し、増殖する。ウイルスベクターは、遺伝子操作によって複製および増殖能を欠損または抑えたウイルスで、目的とする遺伝子をウイルスに組み込むことで、標的細胞に目的遺伝子を効率的に導入し、発現させることがきる。
*5:グリア細胞
脳に分布する非神経細胞の一種で、脳内のグリア細胞の数は神経細胞の数をはるかに上回る。その機能はグリア細胞の種類によって異なるが、神経伝達物質の取り込みやイオン環境の維持、血液脳関門や髄鞘の形成、損傷を受けた神経細胞の除去など多岐に渡る。認知症を含む神経変性疾患患者の脳では、グリア細胞の異常増殖が起こっており、病因および病態に関わると考えられている。
【薬理学分野HP】
https://www.tokyo-med.ac.jp/pharmacol/top.html
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報・社会連携推進室
住所 : 〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1
TEL : 03-3351-6141(代)
E-mail : d-koho@tokyo-med.ac.jp
詳細はこちら
詳細や最新情報は、必ずオフィシャルサイトでご確認ください。
オフィシャルサイトはこちら
データ提供:大学プレスセンター
【東京医科大学】 前頭側頭型認知症治療に向けたプログラニュリン補充療法の生体への影響を解明~ プログラニュリン補充療法の安全性向上への応用に期待~