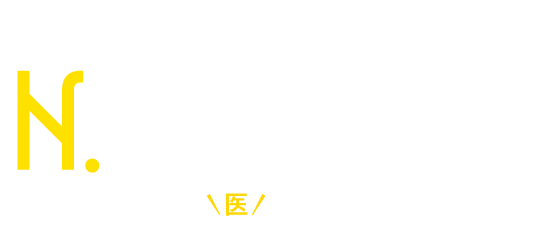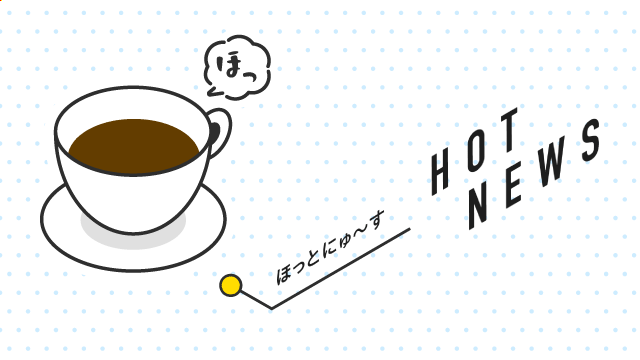イントロ
原作は『BE・LOVE』(講談社)にて、2011年から2018年まで連載された医療漫画。主人公は、産休の養護教諭の代わりに産休補助教員として小学校の保健室を預かることとなった牧野。彼は赴任する前までは帝都大学附属病院の小児科医だったが、愛想の無さと口のきき方の悪さ、態度の大きさを問題視されていた。そのため、学校に専門医を試験配置することを決定した医師会からの要請という口実で、小学校に異動させられたという背景をもつ。子ども達の未来を守る最後の砦たる保健室を舞台に、小学校に赴任した仏頂面の「学校医・牧野」が、類稀なる観察眼で異変を見抜き子供達と父兄を救ってゆく物語。
原作をベースに、2024年10月より日本テレビ系列にてテレビドラマが放送中。ドラマでは、小児科医の牧野を松下洸平が演じ、「学校医」として東多摩第八小学校に赴任した場面から始まる。医師を学校に常駐させるという新たな試みで大学病院から送られた、口も態度もでかい小児科医・牧野が、その観察眼で「言葉にできないSOS」を見抜き、未来へ向かう子ども達の背中を押す保健室ヒューマンドラマとなっている。
作中の病気あれこれ
・ナルコレプシー
ストーリー(第1話)
その日、いつものように保健室にやってきた児童の野咲ゆき。授業中によく居眠りをしてしまうゆきは、保健室で寝ることが常態化していた。突然の居眠りは、先生や母親からの理解ももらえず、友人関係も怪しくなり、一人塞ぎ込むようになっていく。そんな中、ゆきがグラウンドで倒れたという知らせが・・・牧野がくだした診断は果たして―――。
病気の概要
人が昼間の目が覚めた状態で活動できるのは、脳内にある覚醒物質のはたらきがあるからです。そのはたらきの一つに、オレキシンという物質があります。ナルコレプシーの場合、何らかの原因でそのオレキシンを作っている神経細胞が障害されて発病すると考えられています。ナルコレプシーの人にある脳脊髄液にあるオレキシン濃度を調べると、低下していること自体は分かっていますが、それにいたる詳しいメカニズムは解明されていません。
ナルコレプシーの代表的な症状は、
➀、日中突然眠ってしまう「睡眠発作」
寝不足の時や午後2時ごろには誰でも眠くなりますが、ナルコレプシーの症状は、例えば会議のプレゼン中に寝てしまう、自転車をこいでいる最中に寝てしまう、試験中に寝てしまう、野球の試合中守っている間に寝てしまう、といった通常考えにくい場面での「睡眠発作」です。
➁、「情動脱力発作」(喜びや驚きといった強い情動をきっかけに全身の力が抜けてしまう発作)
➂、「睡眠麻痺」(いわゆる金縛り)
が挙げられます。
治療法としては、薬物療法が有効です。しかし、まずは生活サイクルを規則的に整えることが大切となります。それぞれの病気の特徴に合わせた計画的な休憩や仮眠、規則的な夜間睡眠の確保などを行うことができれば、治療に大きく役立っていきます。
調べて納得
ナルコレプシーは、病気の1つです。通常ならば寝てはいけない重要な場面でも、我慢できないほどの強い眠気に襲われたり、突然眠ったりすることが特徴です。病気であるにもかかわらず、「居眠り病」などと言われているように、「だらしない」「真面目にやっていない」などと思われ、本人や周囲が病気と認識しないまま、誤解や偏見に苦しむことが多々あります。日本では、600人に1人がナルコレプシーであるといわれており、10歳代~20歳代前半に多いです。治療が遅れると社会生活に支障をきたす恐れがあるため、早期に治療を開始することが重要なのです。
今回のドラマでも、保健室から教室に戻る野咲ゆきにクラスメイトは「やっぱり仮病かよ」と声を掛けます。もどかしくなって泣き始めたゆきは、ナルコレプシーの発作により、全身の力が抜けて倒れそうになります。そこで牧野が言った言葉が印象的です。「周囲の人間が病気を知らないことで、知らず知らずのうちに当人を追い詰める。今お前たちがやってることがそうだよ」
自分が病気になった時は必死に調べるのに、他人の病気への理解ができていたかと、ふと自問させられました。病気には医者も周囲の人間もみんなのサポートが必要なのだと改めて気づかされました。
ナルコレプシーについては、NPO法人日本ナルコレプシー協会というサポート機関もあります。これを機に病気について調べてみるのもいいかもしれません。
次回予告
Part 4では同じくドラマ内で扱われた病気について詳しく見ていこうと思います。乞うご期待ください。
【話題の医療ドラマ】